テレビアンテナの設置を検討される際、ケーブルの色について疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。特に「白いアンテナケーブルはすぐに劣化してしまう」という話を耳にすることがあります。実際のところ、白いケーブルの寿命はどれほどのものなのか、またなぜ屋外用ケーブルは黒が主流なのかを詳しく解説します。
屋外に設置されたケーブルは、直射日光に含まれる紫外線(UV)によって劣化します。紫外線がプラスチックの分子を破壊し、ひび割れや粉状の劣化(チョーキング現象)を引き起こすのです。
黒いアンテナケーブルにはカーボンブラック(炭素黒)が含まれており、これが紫外線を吸収・分散する役割を果たします。そのため、内部の素材がダメージを受けにくく、白いケーブルに比べて耐久性が大幅に向上します。
「黒は熱を吸収しやすいから、逆に劣化が進むのでは?」と疑問に思われるかもしれません。しかし、カーボンブラックには熱を分散し、均一に放出する効果があります。
屋外に設置されたケーブルは、日中の高温と夜間の低温の繰り返しによって膨張・収縮を繰り返します。これがひび割れ(クラック)の原因となるのですが、カーボンブラックが熱を均一に拡散することで温度変化によるストレスを抑え、長寿命化につながるのです。
ゴムや塩化ビニル(PVC)製のケーブル被覆は、酸素やオゾンと反応することで酸化劣化を起こしやすくなります。カーボンブラックにはラジカルを吸収して酸化の連鎖反応を抑える効果があり、これにより屋外での長期使用でも劣化を遅らせることができます。
ラジカルとは、不対電子を持つ非常に反応性の高い分子のことです。これが周囲の物質と反応することで、酸化や分解が進行します。紫外線や熱によって生成されやすく、ゴムやプラスチックの劣化の原因になります。カーボンブラックはこのラジカルを吸収・安定化することで、酸化の進行を防ぎます。
結論から言うと、白いケーブルでも高品質なものであれば比較的長持ちします。 しかし、次の点を考慮する必要があります。
当社では、以前は外観に合わせて白いケーブルも積極的に使用していました。高品質なケーブルを選んでいましたが、結局、白いケーブルは汚れやすい、劣化が目立ちやすいなどの欠点もありました。そのため、現在では屋外配線については黒いケーブルを使用することを推奨しています。
白いケーブルがすぐにダメになるというわけではありませんが、
近年、アンテナ工事での「防水処理ミス」が原因となり、外壁が深刻なダメージを受ける事例が増えています。特に寒冷地では、わずかな水分浸入が冬季の凍結・融解を繰り返すことで、サイディングを内部から破壊し、建物の寿命を大幅に縮めてしまうケースが少なくありません。以下は、その深刻さを物語る実例の一つです。
窯業系サイディングの凍害による損傷
— CONCEPT建築設計です(金沢市) (@hashinet) September 28, 2024
こちらは 既に解体した家のサイディングです
築22年の家ですが 雪の吹き付ける方向と 雪の乗る下屋周りのサイディングの損傷が酷いです
釘の周りも吸水して凍結して爆裂しています
ここまで行くと補修は不可能なんです
このような事例、北陸は本当に多いです pic.twitter.com/0pf76nUVCy
このような事態を防ぐには、アンテナ工事時に正しい防水処理を行うことが不可欠です。しかし、多くの工事業者が「ビス頭にコーキングをのせるだけ」といった不十分な処置にとどめており、その結果として外壁の劣化を招いている現実があります。本コラムでは、外壁を長く健全に保つための「正しい防水処理」と、法令に則った安全・確実な施工の重要性について、当社の施工事例や他社との比較を交えながら詳しく解説していきます。
アンテナ工事において、しばしば見受けられる誤った施工方法の一つが「ビス頭にのみコーキングを施す」処理です。一見するとビス部分がしっかり保護されているように見え、消費者は「ちゃんと防水対策がされている」と安心してしまいがちです。しかし実際には、ビス頭だけにコーキングしても、壁とアンテナ金具の隙間から水分が侵入します。その水分は毛細管現象などによってビス穴へ引き込まれ、内部でサイディングを破壊してしまう可能性があるのです。
なぜこのような不十分な手法が広まったのでしょうか?一つの背景には、かつて変成シリコーンコーキングが一般的に流通しておらず、安価な標準シリコーンコーキングのみが主流だった時代があります。当時はクリア(ほぼ透明)の変成シリコーンが入手困難で、色合わせの手間やコストもかさみました。しかし現在は、クリアタイプの変成シリコーンコーキングが入手可能になっており、当社(株式会社クラウンクラウン)ではこれを積極的に採用しています。
とはいえ、標準シリコーンコーキングは変成シリコーンコーキングに比べて5~7倍ほど安価で、まとめてビス頭にコーキングを打つだけの簡便な作業工程によって、大量施工や低価格工事を実現できてしまいます。その結果、長期的な建物保護よりも即時的なコスト削減を優先する業者は、今なおビス頭コーキングという誤った防水方法を続ける傾向があります。
当社は、ビス穴内部へ変成シリコーンコーキングを施す正しい防水処理法や、防錆効果の高いビスの使用によって、外壁の長寿命化を実現しています。短期的なコストだけを追求するのではなく、建物全体の健全性を守るための施工こそが、結果的にオーナー様の資産価値を高めると確信しています。
【よくある間違った施工例】一見、防水対策がなされているように見えますが、実際にはビス頭部分にのみ一般的なシリコーンコーキングを塗り付けただけです。これでは壁面とビス穴を十分に保護できず、水分が内部へ侵入してビスの錆やサイディング破損を引き起こすリスクが高まります。
外壁に何かをビスで固定するとき、ビス頭にコーキングをしても壁の中でビスは錆びてしまいます。できればステンレスビスの使用と、下穴をあけてビスにコーキングを塗り付けると錆は防ぎやすくなります。防水の観点からもお勧めですよ。写真は新築時の施工から2年。#おうちのこうじtips pic.twitter.com/OSb3TDLRm9
— 頑張る業者さんを応援するプラットフォーム おうちのこうじ.com (@uchi52com) January 16, 2022
外壁を長く健全に保つためには、単にビス頭へコーキングを施すのではなく、「ビス穴内部」に適切な防水処理を行うことが欠かせません。当社では、ビスを打ち込む前に下穴を開け、内部の切粉や粉塵をハンドブロワーで丁寧に除去したうえで、変成シリコーンコーキングをビス穴に充填します。この手間をかけることで、ビス周りに水分が侵入する経路を確実に断ち、外壁内部への湿気・水分トラブルを根本から防ぐことができるのです。※ビス穴が小さい場合はビス本体に変成シリコーンコーキングを塗り付けてビスを打ちこんでいます。
また、当社ではステンレスやステンレス相当の防錆効果があるビスを採用しています。これにより、たとえ微量の水分が浸入した場合でも、ビス自体が錆びにくくなり、内部での膨張によるサイディング破損や防水性能低下を大幅に抑えることが可能です。さらに、ビス頭部分から発生した錆が雨水に混ざって外壁を汚すようなトラブルも防ぎ、美観を長期的に維持できます。費用面では多少の負担増がありますが、「建物を守る」という観点から見れば、防錆効果の高いビスの導入は非常に価値のある投資といえるでしょう。
一見すると面倒に感じられるこの工程は、長期的な安心と建物価値の維持につながります。当社が変成シリコーンコーキングを積極的に導入しているのは、決して「手間」や「コスト」だけが理由ではありません。「建物を長期的に守る」というポリシーのもと、高品質な材料と確実な施工プロセスを追求し、オーナー様が安心して暮らせる環境を提供するための選択なのです。
アンテナ工事における防水処理を語るうえで、石綿(アスベスト)を含む建材への対応は、見過ごせない要素です。一般住宅には石綿が使われていないと決めつける業者もいますが、実際にはモルタル仕上げ材や古い窯業系サイディングなど、石綿含有の可能性がある建材は確かに存在します。こうした建材に接する工事は、建物解体時だけでなく、改修工事においても法的に事前調査が義務付けられており、2023年10月1日以降は国家資格を有する専門調査者による確認が必須となりました。
「建築物石綿含有建材調査者」や「石綿作業主任者」などの国家資格保有者が関わることで、石綿含有の有無を正確に特定し、粉塵飛散を防ぐための適切な対策を講じることが可能です。これらを軽視すれば、施工現場の安全性はもちろん、防水処理を含む全体的な施工品質にも疑問符がつきます。しかし、法令順守と資格保持を徹底する業者は、こうした“意外な”面にも配慮し、建物内部からのダメージを回避。結果的に、防水性能を最大限に引き出し、お客様の資産価値を長期的に確保できるのです。
当社では、これらの有資格者を適切に配置することで、石綿含有建材の調査や対策を自社内で一貫して行える体制を整えています(必要に応じて外注対応も可能です)。法令遵守を実践することで、あらゆる工程の品質が底上げされ、防水処理に関しても安心・確実な施工を提供できると確信しています。
防水処理を正しく行った後も、外壁の状態を長く健全に保つには、定期的な点検や適切なメンテナンスが欠かせません。たとえば、数年ごとにアンテナ固定金具まわりのビスやコーキング部分を目視確認し、亀裂や浮きがないかチェックするだけでも、早期発見・早期対処が可能です。また、外壁全体の洗浄や塗装の塗り替えを行う際には、防水処理を行った箇所との相性(変成シリコーン使用部位の塗料付着性など)を考慮し、トータルで外壁の健康状態を維持することが重要となります。
さらに、環境条件(降雪地域や海風が当たる地域など)によって劣化要因は異なります。こうした外部要因を踏まえたメンテナンス計画を立て、必要に応じて信頼できる施工業者に相談すると、外壁寿命をより長く引き伸ばせるでしょう。定期点検と適切な対策の積み重ねが、建物の資産価値を保ち、安全で快適な居住環境を持続させる鍵となります。
アンテナ工事時の防水処理は、ビス穴への適切なコーキングや防錆ビスの使用、そして石綿含有建材調査などの法令遵守を含め、建物の長寿命化に欠かせない重要な要素です。誤った防水処理は、サイディング内部での水分侵入やビスの錆による膨張・破損を招き、外壁寿命を大幅に縮めてしまいます。一方、正しい防水処理と資格・法律に基づいた施工を行うことで、外壁の健全性と美観、ひいては建物の資産価値を長期にわたり守ることが可能です。
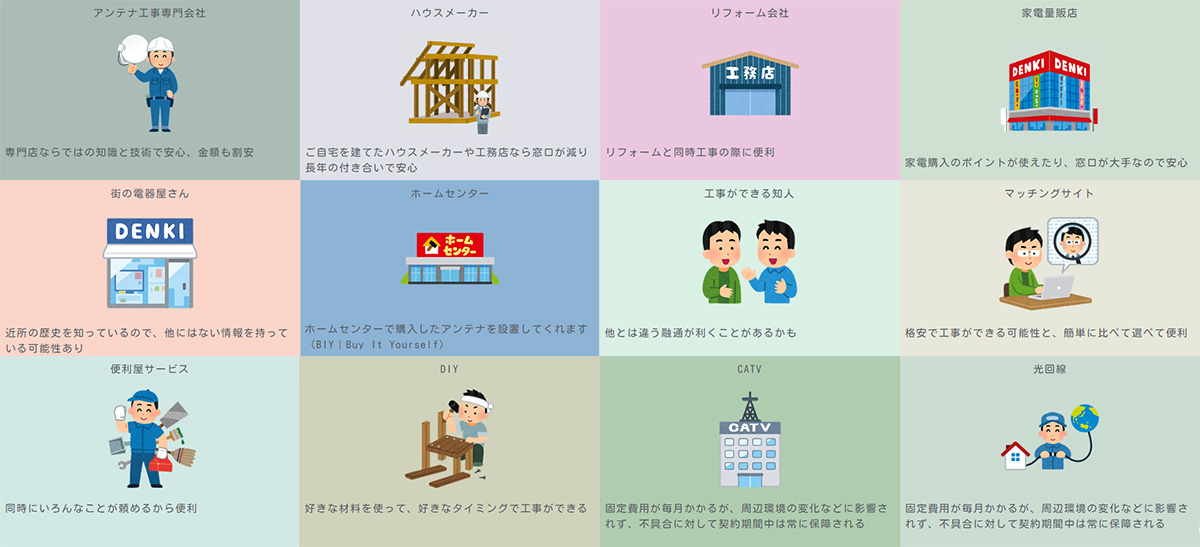
集合住宅から戸建てに移り住むときに、アンテナのことはあまり考えない方が多いかとは思います。
特に屋根の上にアンテナが立っていればそのままテレビが映るものと考えがちですが、実際には映らなくて困ったというご相談をたびたび受けます。
このコラムでは、ご自身でできる確認方法と対策・対処方法、どういった場合にプロを呼ぶ必要があるのかなどを解説します。とりあえず相談したいという場合でも弊社では無料のご相談(電話またはメール)を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
さまざまな問題解決に役立つよう、ボリュームのあるものとなっております。目次から必要そうな項目を探し出し、そこから読み進めていっていただいても大丈夫です。
このコラムではTOKYO MX(東京MXTV:以下MXTV)を受信したい(視聴したい)方のための情報まとめとなります。
現時点でMXTVが受信できない、安定して映らないなどの方の対処法から、これからアンテナを立てるときにMXTVを受信するためにはどうすればいいかなどをアンテナ工事のプロの視点からまとめました。
さらに、2025年最新情報として、最新型ブースターと旧型ブースターの使い分けなどについても解説します。
東京MXは東京のローカルチャンネルで、リモコン番号9番の地デジ放送です。
正式名称は東京メトロポリタンテレビジョン、愛称はTOKYO MX、略称はMXTV(当社のコラムや施工事例ではTOKYO MXもしくはMXTVと表記しています)。
その他詳しい情報はwikipediaをご参照ください。
関東では一般的に民放キー局5局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ)とNHK2局(総合、Eテレ)(※以下まとめて基本チャンネル)を受信・視聴されていることが多いと思います。
これに加えて、ローカルチャンネル(ローカル局・地方局)としてTOKYO MX、テレ玉(テレビ埼玉)、TVK(テレビ神奈川)、チバテレ(千葉テレビ)、とちテレ(とちぎテレビ)、群馬テレビなどを同時に視聴したいという方も多くいらっしゃると思います。
実際にこれらを受信するにはどうしたらいいのでしょうか。
2019年12月の最新事情を追記しています。
(さらに…)
台風や突風でアンテナが倒れる・曲がるといった被害は、毎年のようにご相談いただきます。実はこうした被害は、火災保険の「風災補償(ふうさいほしょう)」でカバーされる場合があります。本記事では、風災補償の仕組みから請求の注意点、実際の工事・費用相場、注意すべき業者まで詳しく解説します。